金剛寺について
歴史
応永元年(1394)開創。
本尊は延命地蔵菩薩。開山(初代住職)は季高法雲(きこうほううん)禅師で当初は黄龍山(こうりゅうざん)金剛寺といいました。 宗旨は鎌倉円覚寺に本山を構える臨済宗円覚寺派に属す禅寺です。文安2年(1445)北条早雲の前の小田原城主、大森氏頼(うじより)が伽藍を整備拡充して寺格を高めて、山号も祥龍山と改称しました。この時より大森氏の家紋である二つ巴が寺紋に定められました。
本尊は延命地蔵菩薩。開山(初代住職)は季高法雲(きこうほううん)禅師で当初は黄龍山(こうりゅうざん)金剛寺といいました。 宗旨は鎌倉円覚寺に本山を構える臨済宗円覚寺派に属す禅寺です。文安2年(1445)北条早雲の前の小田原城主、大森氏頼(うじより)が伽藍を整備拡充して寺格を高めて、山号も祥龍山と改称しました。この時より大森氏の家紋である二つ巴が寺紋に定められました。

嘉永6年(1853)の小田原地方大地震で本堂や庫裡は全部潰れてしまいました。
安政元年(1854)庫裡が再建されて,本堂は慶応3年3月(1867)に鎌倉円覚寺の塔頭(たっちゅう)である続灯庵(ぞくとうあん)の本堂に型取って再建されました。塔頭とは本山境内にある寺院のことで、もともとは高僧のお墓を守るための坊、または高僧が暮らしていた庵のことをいいます。
続灯庵は金剛寺の開山、季高法雲の師である円覚寺30世大喜法忻(だいきほうきん)のために建てられたお寺で、塔所(お墓がある場所)でもあります。
安政元年(1854)庫裡が再建されて,本堂は慶応3年3月(1867)に鎌倉円覚寺の塔頭(たっちゅう)である続灯庵(ぞくとうあん)の本堂に型取って再建されました。塔頭とは本山境内にある寺院のことで、もともとは高僧のお墓を守るための坊、または高僧が暮らしていた庵のことをいいます。
続灯庵は金剛寺の開山、季高法雲の師である円覚寺30世大喜法忻(だいきほうきん)のために建てられたお寺で、塔所(お墓がある場所)でもあります。

戦争中に金剛寺に疎開してきた子供たちです。正面奥に見える茅葺屋根が本堂です。左側は観音堂、右側には庫裡が見えます。

昭和21年当時の本堂は再建当初の茅葺屋根でした。

桃源の庭

ハクモクレン

昭和30年頃の参道
本尊様
金剛寺の本尊は延命地蔵菩薩(えんめいじぞうぼさつ)というお地蔵さんです。お地蔵さんの原名はクシティ・ガルバといいます。クシティは大地、ガルバは母のお腹の中という意味です。大地が万物を育む力を備えている母の体であるように、お地蔵さんも無限の福徳を包み備えていて全てのものに利益を与えられているのでこの名が付いたとされています。弱いものから真っ先に救って下さるということで昔から子供の守護尊とされ、子供や水子供養、または安産のご利益で知られています。延命地蔵の名は新しく生まれた子供を守り、その寿命を延ばすことから由来するとされています。当寺のお地蔵さんにも昔は安産護符を請願された方が沢山いらっしゃったそうです。


シャム佛
小田原の北条早雲の前の小田原城主、大森信濃守氏頼入道寄栖庵(おおもりしなのかみうじよりにゅうどうきせいあん*注.)のご念持佛で釈迦如来(高さ7寸7分 金佛)
シャム国(現在のタイ王国)より渡来してきたもので世人呼んでシャム佛といいます.これは当時,小田原とシャム国交のあった証拠として
貴重な存在となっています.どいう経路で金剛寺に安置されたのでしょうか?
金剛寺が開創して51年後に氏頼が中興してから大森氏紋である二つ巴を寺紋と定むと記録されています。
当時の住職,2世鉄外和尚は老後の隠居寺(未寺)として大日山禅慶庵(善慶庵とも書かれています)を創立して寄栖庵の秘佛を本尊として安置したとあります。
その禅慶庵は小田原攻めの際,焼滅してしまいました。以来,当寺に移されたと伝えられています。
*注.大森氏頼は跡継ぎに小田原城を譲った後、自身を寄栖庵と名乗り岩原城に入った。大森氏頼は、明応3年に死去。
シャム国(現在のタイ王国)より渡来してきたもので世人呼んでシャム佛といいます.これは当時,小田原とシャム国交のあった証拠として
貴重な存在となっています.どいう経路で金剛寺に安置されたのでしょうか?
金剛寺が開創して51年後に氏頼が中興してから大森氏紋である二つ巴を寺紋と定むと記録されています。
当時の住職,2世鉄外和尚は老後の隠居寺(未寺)として大日山禅慶庵(善慶庵とも書かれています)を創立して寄栖庵の秘佛を本尊として安置したとあります。
その禅慶庵は小田原攻めの際,焼滅してしまいました。以来,当寺に移されたと伝えられています。
*注.大森氏頼は跡継ぎに小田原城を譲った後、自身を寄栖庵と名乗り岩原城に入った。大森氏頼は、明応3年に死去。

馬頭観音
重機や車がない時代、人々にとって牛や馬はとても大切な労働力であり、移動手段でした。
馬頭観音はそれらを守る仏として信仰を集めました。
金剛寺の馬頭観音は、経巻をくわえた狐にまたがる江戸時代の仏像。頭上には獣頭を載せ、炎髪をつくる。儀軌(経典などに示された仏像の形)にはない珍しい容姿ですが、寺には馬頭観音として伝えられました。
津久井(神奈川県北西の地区)に住む観音信者の老婆がこの寺でお祀りして欲しいと背負ってきたと、言い伝えにあります。
馬頭観音はそれらを守る仏として信仰を集めました。
金剛寺の馬頭観音は、経巻をくわえた狐にまたがる江戸時代の仏像。頭上には獣頭を載せ、炎髪をつくる。儀軌(経典などに示された仏像の形)にはない珍しい容姿ですが、寺には馬頭観音として伝えられました。
津久井(神奈川県北西の地区)に住む観音信者の老婆がこの寺でお祀りして欲しいと背負ってきたと、言い伝えにあります。

韋駄天
造立年代は江戸末期〜明治時代の仏像です。金剛寺の客殿・庫裡で祀られていますが、一般公開はしておりません。
一昔前まで、足の速い人のことを韋駄天と呼んだりしたように、非常に足の速い伽藍の守護神です。
元々はインドの神様で、お釈迦さまのお骨を盗んだ鬼を追っかけて捕まえたという伝説や、お釈迦さまのために方々を駆け巡って食べ物を集めたという伝説があり、「ご馳走」という言葉はここから来ているとも言われています。
禅宗の寺院では庫裡や台所などの生活スペースにお祀りされ、建物を守っています。
一昔前まで、足の速い人のことを韋駄天と呼んだりしたように、非常に足の速い伽藍の守護神です。
元々はインドの神様で、お釈迦さまのお骨を盗んだ鬼を追っかけて捕まえたという伝説や、お釈迦さまのために方々を駆け巡って食べ物を集めたという伝説があり、「ご馳走」という言葉はここから来ているとも言われています。
禅宗の寺院では庫裡や台所などの生活スペースにお祀りされ、建物を守っています。

大日如来
元は有名な陶芸家、辻輝子氏の夫である松永健男氏の所有でしたが、健男氏が仏像を永く守れる場所を探していたところ、18世和尚とのご縁で金剛寺に寄贈、安置されるに至りました。奈良時代の仏像との云われですが、詳細は不明です。
大日如来は、この宇宙の根本、この世界の森羅万象そのものの象徴とされています。
金色に包まれた荘厳な姿で、手に智拳印を結び、菩提(迷いを離れること)も煩悩(迷いの中にあること)も本来一体であることを表しています。
お彼岸中、お盆中、年末年始などに一般公開しております。
大日如来は、この宇宙の根本、この世界の森羅万象そのものの象徴とされています。
金色に包まれた荘厳な姿で、手に智拳印を結び、菩提(迷いを離れること)も煩悩(迷いの中にあること)も本来一体であることを表しています。
お彼岸中、お盆中、年末年始などに一般公開しております。
チーム

佐々木壱穂
住職
昭和59年6月4日,金剛寺の先代住職の長男として生まれた私でしたが,小さい頃はお寺に生まれたこと,父がお坊さんであることが嫌でした。弟に寺を継がせると自分で勝手に決めて,大学は”お坊さんにはならない!”という強い意思表示としてキリスト教の大学に進みました。そんな私でしたが先代の体調が優れず,後継ぎの必要性が高まったことをきっかけに悩みに悩んだ末,お坊さんとして寺を継ぐ覚悟を決めました。鎌倉の円覚寺で3年半の修行後,約7年間金剛寺の副住職として努め,令和元年より19代目住職に就任しました。葬儀,法要などの亡くなった方の供養はもちろん大切なのですが,2500年前にお釈迦様が生涯をかけてお説きになった仏教は,人々が心豊かに生きていくための教えです。私はまだ知識も経験も未熟ですが,少しでも皆様の心に寄り添える坊さんを目指していきたい。そして,庭や建物を少しづつ整備してお寺としての雰囲気を高めたい。お参りに来た方が,帰るときには穏やかに澄んだ心で,自然な笑顔で帰っていく。そんなお寺を生涯かけて作っていきたいと思います。
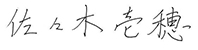

佐々木照子
静岡県の藤枝市のお寺で生まれ,40年前に先代住職の妻になり金剛寺に来ました。趣味は鈴虫の飼育で、30年前に父から鈴虫の入った虫かごをひとつもらったことをきっかけに始めました。今では一箱だった鈴虫が10倍以上に増えて、欲しい人に分ける程になりました。夏から秋にかけて鈴虫の音色が檀家さんを楽しませてくれます。
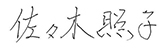

佐々木 Judith
スイスで生まれ,2013年に来日しました。小田原の報徳二宮神社-報徳会館で働いていたときに,今の金剛寺住職に出会いました。現在は金剛寺の一員として,お寺のホームページ、広告、イベント企画などを担当します。


